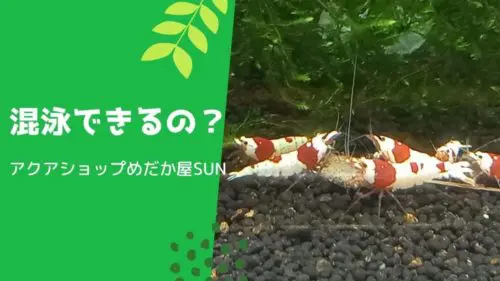レッドビーシュリンプってとても可愛いですよね。
こんなに可愛いシュリンプを、メダカや熱帯業と混泳させることができたら、いっそう水槽が楽しくなりそうって考えたことはありませんか?
私も、混泳ができたらいいなと思ってチャレンジしたことがありますが、なかなか上手くいきませんでした。
今回は、そんなレッドビーシュリンプの混泳について、私が調べて分かったことと、実際の経験を交えながら解説させていただきます。
皆さまは、レッドビーシュリンプを混泳させたり、混泳させてみたいと思ったことはありますか?
私は、メダカやグッピーなどの熱帯魚も飼育していますので、一緒に飼育できたら水槽が賑やかで楽しくなると思ってチャレンジしたこともあります。
結論から申し上げあると、私の実感でレッドビーシュリンプは混泳に向いていません。
今回は、私がなぜレッドビーシュリンプが混泳に向かないと感じるかをご説明させていただきます。
【STEP1】コケ取り用のタンクメイトとして

シュリンプの飼育理由の一つが、コケ取り用のタンクメイトですよね?
レッドビーシュリンプも他のシュリンプ同様、水槽内の苔を食べる生き物です。
ただ、そのコケ取り能力だけを見ると、ヤマトヌマエビやミナミヌマエビと比較して、かなり力不足と言えます。
ヤマトヌマエビやミナミヌマエビに比べて飼育が難しいことも考えると、コケ取り目的でレッドビーシュリンプを導入するのは、とても効率が悪いのでおすすめいたしません。
【STEP2】熱帯魚との混泳について

結論から申し上げて、熱帯魚との混泳は、できないこともないけどデメリットがあるよねって感じです。
カラシンなど小型のメダカ類(ネオンテトラやグッピー・メダカなど)

大型の魚は言うまでもないので割愛します。
ネオンテトラなどが、直接レッドビーシュリンプを攻撃する様子は見たことがありませが、全長が3㎜しかない孵化直後の稚エビは、気が付かない間に捕食されている可能性が否定できません。
水槽内の稚エビそのものが、とても小さくて気が付きにくい存在なので、ここは冤罪かもしれませんが、可能性は高いと思います。
それに、脱皮したてのレッドビーの体はとても柔らかく、イタズラ程度につつかれても致命傷になりかねないので、そういった心配もあります。
シュリンプの隠れ家を作れば安心というご意見も見かけるのですが、私個人の意見としては、水質に敏感なレッドビーの飼育で、餌の食べ残しや死骸等の見落としの原因になる、レイアウト素材を必要以上に水槽に入れることはおすすめいたしません。

レッドビーシュリンプの飼育で水槽に入れるレイアウト素材は、一掴みのウィローモスと、入れてもフウの実くらいにしておく方が安心だと思います。
オトシンクルス
安心なお魚と聞いて真っ先に思い浮かぶのが、壁面の苔のみを食べる温和なオトシンクルス。
恐らく、稚エビを捕食することもなさそうだから、オトシンクルスが混泳に向いている魚NO.1なのではないでしょうか?
ただ・・・

壁に張り付いて苔を食べるオトシンと、水底と壁面で暮らすシュリンプだけでは、組み合わせとして面白くないですよね。
それに、共に壁面の苔を食べる食性時点で、餌が被っちゃいます。
コリドラス・プレコ
コリドラスは底面を泳ぐナマズ類のお魚で、気質もとても温和ですが食性がシュリンプと重なるんですよね。
レッドビーシュリンプとって、自分より大型なコリドラスと餌を取り合うって、かなりストレスになる可能性が高いと思います。
それに、水槽内の生息エリアも重なるので、やっぱり稚エビの事故が気になるかな・・・。

生き物にとってストレスって、思っている以上に害があるんです!
不要なストレスは避けるに越したことがありません。
【STEP3】他のシュリンプとの混泳

私は未確認ですが、ヤマトヌマエビはレッドビーシュリンプの稚エビを捕食する噂があります。
可哀そうだから、実験したことはありません。
黒ビーやシャドウ系、ハイブリッド系シュリンプとの混泳は交雑がデメリット?
交雑も品種改良みたいで楽しいと思えばメリットですよね。

交雑しない種類のシュリンプ同士の混泳では、餌と生活スペースを種ごとに奪い合い、最終的に種として弱いシュリンプが淘汰されると伺ったことがあります。
それを聞いてから、基本的に違う種類のシュリンプは混泳しないようにしています。

最初にも申しましたが、結論レッドビーシュリンプは混泳に向かないと思います!