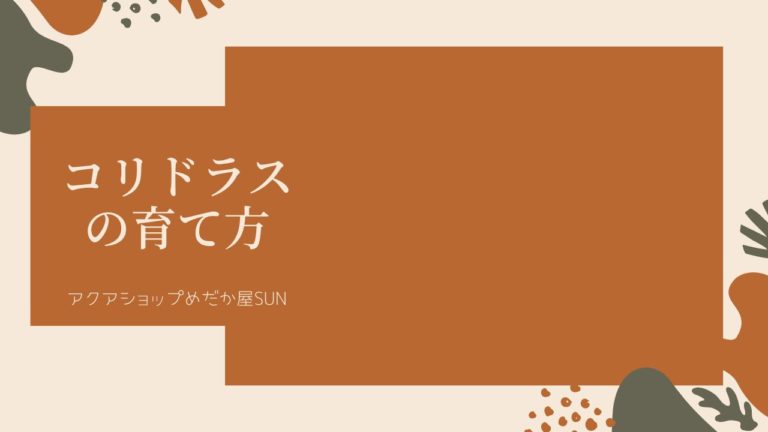みなさま、コリドラスの飼育を楽しんでいらっしゃいますか?
とても可愛いコリドラスですが、他の観賞魚のタンクメイトとして飼育していて、特にコリドラスついて深堀されていない方が多いのではないでしょうか?
コリドラスが1日の大半を過ごす水底は、水槽の中でも最も汚れやすい場所で意外に過酷なんですよ。
そのため、コリドラスが強い魚と過信していると、水カビやヒレ腐れ病に罹患させてしまうこともあり危険です。
今回は、油断しがちなコリドラスの飼育について解説させていただきます。
いきなりですが、コリドラスの飼育って意外に油断しがちで、気が付くと水カビなど病気に罹患して慌てた経験はありませんか?
コリドラスは水槽の中で脇役になる事が多く、結構タフな魚であることもあり飼育が雑になってしまった方も多いのではないでしょうか?
でも、コリドラスが生活する水底は、水槽の中でも最も汚れやすい場所なので、油断していると水質汚染でコリドラスが病気になってしまいます。
今回は、じっくり観察するととても可愛いコリドラスの育て方について解説をさせていただきます。
【STEP1】水質面での環境作りや水替えについて

コリドラスが好むのは水温20℃~25℃の弱酸性~中性の軟水です。

飼育水が弱酸性と聞いてパッと浮かぶのがソイルですよね?
でも、コリドラスはソイルを掘ったり砕いたりする習性があり、ソイルをダメにしてしまうので使用は避けた方がいいです。
基本的にコリドラスの低床材は以下のような砂利や砂の使用をおすすめします。

初心者の方には、使用前の予洗いが不要でろ過バクテリアが添加されている「GEXナチュラルパウダー」がおすすめです。
この砂を使用されると水槽の立ち上がりを速めることができます。
phを調整する方法

コリドラスは中性から弱酸酸性の水質を好むので、低床にはphへの影響が少ない田砂などを使用して、弱酸性~中性で管理する方が楽だと思います。
YOUTUBEの動画を見てもコリドラスは砂で飼育されていることが多いですよね?
基本的に水質を弱アルカリ性に誘導しない素材であれば低床に使えますが、水底を這うよに泳ぐコリドラスを傷つけないためには、砂や粒の小さな砂利などを使用する方が安心です。

砂利の中にはphを弱アルカリ性に誘導するものがあるので、説明をしっかり読んで選んでくださいね!
金魚などで一般的な砂利は、石に混ざっている貝殻のカルシウムで水質が弱アルカリ性になるので、コリドラスの飼育には向いていません。

すごく大雑把ですが低床材と水質の関係です。
土っぽいものを使えば弱酸性になり石っぽいものを使うと弱アルカリ性になります。
低床にソイルを敷いていても、石や岩をたくさんレイアウトしてしまうと適度な弱酸性でなくなる可能性があるのでご注意ください。


phは観賞魚飼育の中でも凄く大切な要素なのでご注意ください。
詳細については以下の記事でご確認いただけます。
水替えについて

コリドラスはよく食べてよく糞をするので水を汚し易いです。
また、先ほども書きましたが水底の付近は水が停滞して汚れが溜まりやすいので、他の観賞魚に比べて多めに水替えをするほうが安心です。

私は魚の調子を見ながら、少なくとも2日に1回1/4程度の水換えをするようにしています。
観察していて元気がない時は、昨日水替えをしていても続けて水替えをしてあげてください。

水替え時の注水は、点滴容器を使う方が安心です。
水底の水質維持については、エアレーションの記事をご確認ください。
【STEP2】水温について

コリドラスの水温は20℃~25℃が適温と言われていて、私はエアコンで常時24℃に管理しています。
高温は30℃まで耐えたとの話も聞きますが、魚へ与える負担が大きいのでご注意ください。
また、水温が下がると白点病が出るリスクが高まるので、24℃くらいを維持できるようにご対応下さい。

白点病については以下の記事をご覧ください。

どうしても水温が28℃を超えそうな場合は、アクアリウム用の冷却ファンをお使いください。
費用は掛かりますが大切なコリドラスが全滅するよりはマシだと思います。

冬の寒さは温度が固定の安価なものでよいので、アクア用のヒーターで対応してください。
このヒーターでしたらパワーが160Wで水温15℃~32℃で調整できるので、ある程度の大きな水槽でも十分お使いいただけます。

水温計はDaisoの物でも十分ですが、温度が見やすいデジタル水温計があると管理がしやすいのでおすすめです。
温度が間違っているとそれだけで全滅のリスクがあるので、温度計やヒーターに関しては信頼できるメーカーさんの商品が安心だとい思います。
【STEP3】餌について
コリドラスの餌は市販のペレットの他に、冷凍赤虫をあげると争うように食べてくれます。

私はペレットをメインにして、おやつ程度に冷凍赤虫を与えています。

冷凍赤虫は活き餌に比べて使いやすいのでおおすすめですよ。
ただし、ペレットに比べて水を汚しやすいので、底に余った赤虫は必ずピンセットなどを使用して取り出してください。

冷凍赤虫だけでなく活き餌にチャレンジされたい方は以下の記事を合わせてお読みください。
難しそうに見えますが、コツをつかめば難しいことはありません!